💡 記事の概要
日本には、すべての国民がいずれかの医療保険に加入する**「国民皆保険制度」があります。その中で主なものが「国民健康保険」と「健康保険(社会保険)」です。この2つの制度は、私たちが病気やケガをした際の医療費を助けてくれる大切な仕組みですが、「誰が加入するのか」「保険料はいくらなのか」「どんな時にどんな保障を受けられるのか」**という点で大きな違いがあります。
この記事では、国民健康保険と健康保険の違いを**「保障」「お金」「加入」**という3つの視点から徹底比較。会社員と個人事業主(事業主)それぞれの立場から、メリットとデメリットを分かりやすく解説していきます。あなたの働き方に合った医療保険制度を理解し、いざという時に困らないための知識を身につけましょう。
基本的な制度の違い:あなたはどちらに当てはまる?
まず、どちらの保険制度に加入することになるのか、その対象者を見ていきましょう。
加入対象者
- 国民健康保険: 自営業者、個人事業主、フリーランス、無職、年金受給者など、会社に属していない人や、他の医療保険制度に加入していない人が対象です。
- 健康保険(社会保険): 会社員、公務員、教職員とその扶養家族が加入対象です。企業に勤める従業員が加入する「協会けんぽ」、大企業の従業員が加入する「組合健保」、公務員が加入する「共済組合」などがあります。
ポイント: 会社に雇用されているかどうかが、どちらの保険に加入するかの大きな分かれ目になります。
保障部分の違い:万が一の時の安心感は?
病気やケガの際に受けられる保障内容も、両者で違いがあります。
基本的な医療保障
両制度とも、医療費の自己負担割合は基本的に同じです。
- 6歳未満: 2割負担
- 6歳以上70歳未満: 3割負担
- 70歳以上75歳未満: 2割負担(現役並み所得者は3割)
- 75歳以上: 1割負担(現役並み所得者は3割)
現金給付の大きな違い
医療費の自己負担割合は同じですが、**病気や出産で働けなくなった際にもらえる手当(現金給付)**に大きな違いがあります。
- 傷病手当金
- 健康保険: あり(病気やケガで仕事を休んだ際、標準報酬日額の2/3を最大1年6ヶ月支給)
- 国民健康保険: 原則なし(一部の国保組合で任意給付として実施している場合もありますが、一般的ではありません。)
- 出産手当金
- 健康保険: あり(出産のために仕事を休んだ際、標準報酬日額の2/3を産前42日・産後56日支給)
- 国民健康保険: 原則なし(一部の国保組合で任意給付として実施している場合もありますが、一般的ではありません。)
高額療養費制度
両制度とも高額療養費制度は利用可能です。1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、超過分が払い戻されます。これにより、高額な医療費がかかっても自己負担を抑えることができます。
ポイント: 健康保険は、病気や出産で「働けない期間の収入を保障する手当」があるため、より手厚い安心感があります。
お金の部分の違い:毎月の保険料はどう違う?
毎月支払う保険料の仕組みは、両制度で大きく異なります。
保険料の負担構造
- 健康保険(会社員)
- 負担割合: 保険料は会社と従業員が半分ずつ負担します。
- 扶養制度: 年収130万円未満の扶養家族がいる場合、追加の保険料負担なしで被扶養者として医療保障を受けられます。
- 計算方法: 給与額を基に算出される「標準報酬月額」に保険料率をかけて計算されます。
- 国民健康保険
- 負担割合: 保険料は全額自己負担です。
- 扶養制度: 扶養の概念がなく、世帯内の国民健康保険加入者一人ひとりに保険料がかかります。
- 計算方法: 前年の所得に応じた「所得割」と、加入者数に応じた「均等割」の合算で計算されます。
具体的な保険料比較(年収300万円の場合のモデルケース)
以下の表は、年収300万円(月収25万円)の場合の、東京都の料率を基にした概算の保険料です。自治体や年度によって異なりますので、あくまで目安として参考にしてください。
| 項目 | 健康保険(会社員) | 国民健康保険 | 差額 |
| 39歳以下・単身 | 12,475円/月 | 27,282円/月 | +14,807円/月 |
| 40歳以上・単身 | 14,475円/月 | 33,484円/月 | +19,009円/月 |
| 40歳以上・3人家族 | 14,475円/月 | 100,451円/月 | +85,976円/月 |
Google スプレッドシートにエクスポート
ポイント: 健康保険は会社が半額負担してくれる上に、扶養家族がいても追加料金がかからないため、特に家族が多い場合は国民健康保険と比較して圧倒的に保険料負担が軽くなります。
加入の部分の違い:手続きはどうする?
保険への加入手続きや保険料の支払い方法にも違いがあります。
手続き方法
- 健康保険(会社員)
- 手続き: 会社が代行してくれます。
- 保険料徴収: 毎月の給与から天引きされるため、支払い忘れの心配がありません。
- 開始日: 入社日から資格取得となります。
- 国民健康保険
- 手続き: 本人がお住まいの市区町村の窓口で手続きする必要があります。
- 期限: 会社を退職したなど、国民健康保険の資格取得事由が発生してから14日以内に手続きが必要です。
- 保険料支払い: 口座振替または納付書で自分で支払います。
- 国民健康保険加入時の必要書類
- 健康保険資格喪失証明書(会社を退職した場合など)
- 本人確認書類
- マイナンバー確認書類
- 銀行口座情報(口座振替希望の場合)
ポイント: 健康保険は会社任せで楽ですが、国民健康保険は自分で手続きや支払い管理が必要です。
会社員と事業主(個人事業主)それぞれのメリット・デメリット
それぞれの制度の特性を踏まえたメリット・デメリットをまとめてみましょう。
会社員のメリット・デメリット
- メリット
- 保険料を会社と折半できるため、実質的な負担が軽減されます。
- 扶養制度があり、年収130万円未満の家族は追加の保険料なしで保障されます。
- 傷病手当金や出産手当金があり、病気や出産で働けない期間の収入が保障され安心です。
- 加入手続きや保険料の支払いが会社によって代行されるため、手間がかかりません。
- 給与天引きなので、支払い忘れの心配がありません。
- デメリット
- 転職や退職時に手続きが必要です。特に退職後は任意継続か国民健康保険への切り替えを検討する必要があります。
- 会社の健保組合によっては給付内容が異なる場合があります。
事業主・個人事業主のメリット・デメリット
- メリット
- 雇用形態に関係なく、継続して加入が可能です。
- 事業が不安定な時期でも、医療保険制度に加入し続けられます。
- 所得が低い場合は保険料の軽減制度が適用されることがあります。
- 手続き自体は比較的シンプルです。
- デメリット
- 保険料が全額自己負担となります。
- 扶養制度がないため、家族が増えるとその人数分の保険料も個別に負担する必要があります。
- 傷病手当金や出産手当金がないため、病気や出産で働けなくなった際の収入保障がありません。
- 所得が高いと保険料も高額になりやすい傾向があります。
- 保険料の支払いを自分で管理する必要があります。
まとめ
国民健康保険と健康保険の最大の違いは、現金給付の有無と保険料の負担構造にあります。
- 会社員にとって健康保険は、保険料の半額を会社が負担し、扶養制度や現金給付も充実している非常に有利な制度です。 万が一の病気や出産時にも、手厚い保障があるため経済的な不安が少ないでしょう。
- 一方、個人事業主の国民健康保険は、保険料の全額自己負担に加え、扶養制度や現金給付がないため、特に家族が多い場合や病気・出産時の経済的負担が大きくなる可能性があります。 ただし、所得に応じた保険料の軽減制度もあり、所得が低い場合は保険料が抑えられることもあります。
自身の働き方や家族構成を考慮して、どちらの制度が自分にとって最適な保障と負担のバランスを提供してくれるのかを理解しておくことが重要です。
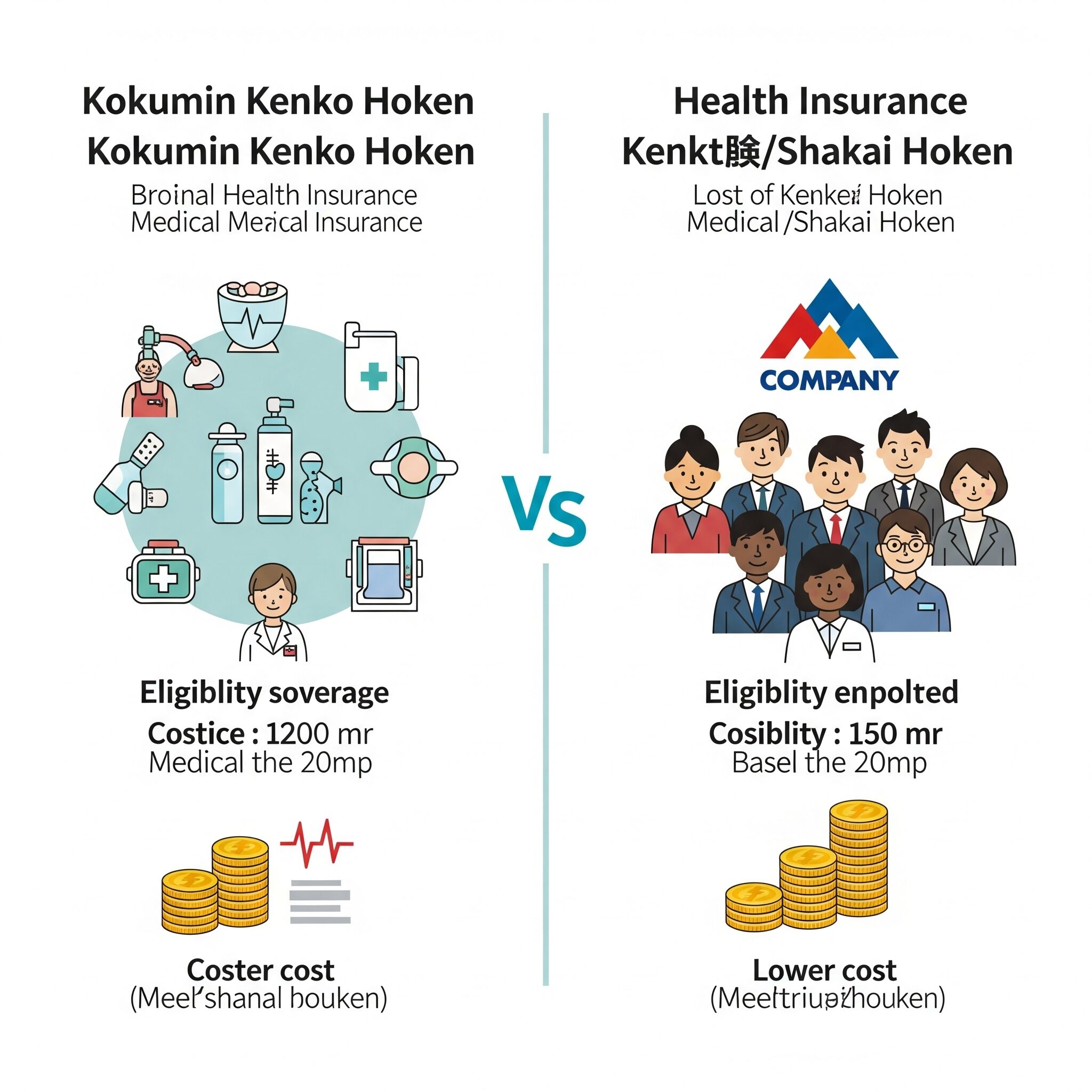


コメント