結論:借主は原則として家賃値上げを拒否できますが、〈賃料不増額特約〉や〈自動改定特約〉を結んでいる場合は拒否できないことがあります。
1. 家賃値上げの法的根拠と借主の権利
日本の賃貸借契約における家賃改定権は、借地借家法第32条(建物の賃料増減請求)に基づきます。
「土地・建物の税負担増」「経済事情の変動」「近傍同種建物の賃料との不均衡」が生じ、現在の家賃が不相当と認められる場合、貸主は将来に向かって賃料増額を請求できます。
しかし、借主には「家賃増額請求を拒否する権利」があり、貸主は借主の同意を得なければ改定できません。合意が得られない場合、従前の家賃で契約は自動更新(法定更新)されます。
2. 拒否できる場合
2-1. 正当事由がない・根拠不足
- 借地借家法第32条所定の「①租税負担増 ②経済事情変動 ③近傍同種賃料との比較」に該当しない
- 理由の開示を求めたが資料(固定資産税通知書等)を示せない
→ 借主は理由の説明を求め、納得できなければ拒否可能。
2-2. 通知手続きの不備
- 通知が書面(内容証明郵便)でない
- 通知時期があまりにも急(入居者に検討時間を与えない)
→ 手続き要件を欠く場合、借主は無効を主張して拒否できる。
3. 拒否できない場合
3-1. 賃料不増額特約(「一定期間賃料を増額しない」との合意)がある
契約時に「○年間は賃料を増額しない」という特約を設けた場合、原則としてその期間内は貸主の増額請求は認められず、借主は拒否できません。
ただし、特約期間中に経済事情が激変し、当事者が予見できないほど不公平と認められる場合には例外的に増額請求が可能と判示された例があります(事情変更の原則)。
3-2. 自動改定特約(インデックス条項等)に基づく増額
「3年ごとに賃料を〇%増額する」「固定資産税増減率に連動して改定する」など、あらかじめ賃料改定ルールを定めた特約は原則有効で、借主は自動的に改定される賃料を拒否できません6。
ただし、その定めが不明確・不合理であったり、激変事態では事情変更の原則が適用され得ます。
4. 拒否後の流れと交渉のポイント
- 貸主に書面で理由開示を請求
- 近隣相場や課税資料を借主自身で調査
- 交渉
- 増額幅や実施時期の見直し
- 設備改善等の条件設定
- 合意形成困難なら従前家賃を支払い、裁判・調停で争う
裁判になると、確定までの間は「相当額」を支払えば足ります。
5. まとめ
家賃値上げは借地借家法に基づく「賃料増減請求権」によるものですが、借主には拒否権があり、貸主は借主の同意を得なければ値上げできません。
ただし、契約で「一定期間増額しない」「自動改定」の特約を結んでいる場合は借主は拒否できず、例外的に事情変更の原則で争う必要があります。
まずは通知理由と手続きの妥当性を確認し、根拠が乏しければ拒否・交渉を検討しましょう。
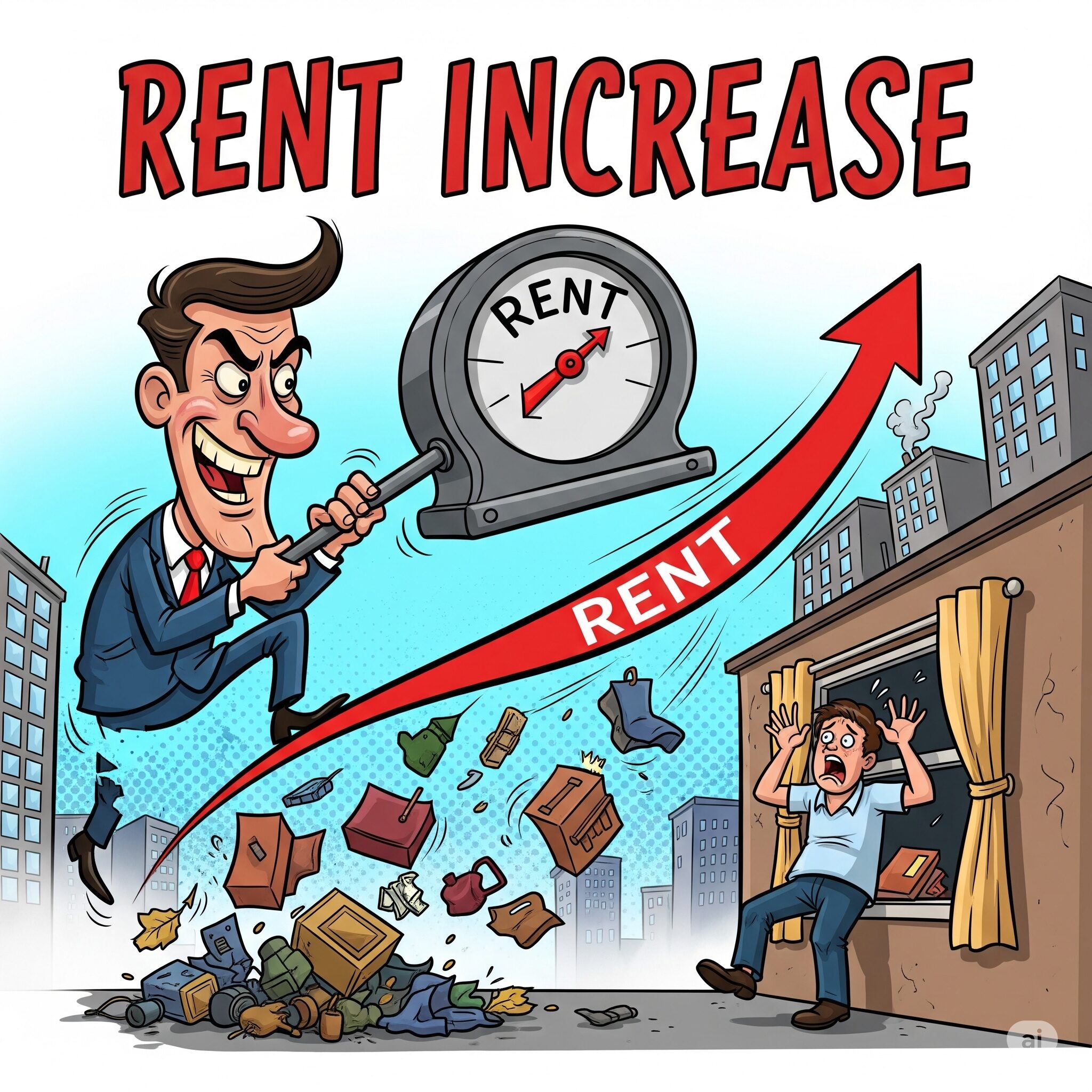


コメント